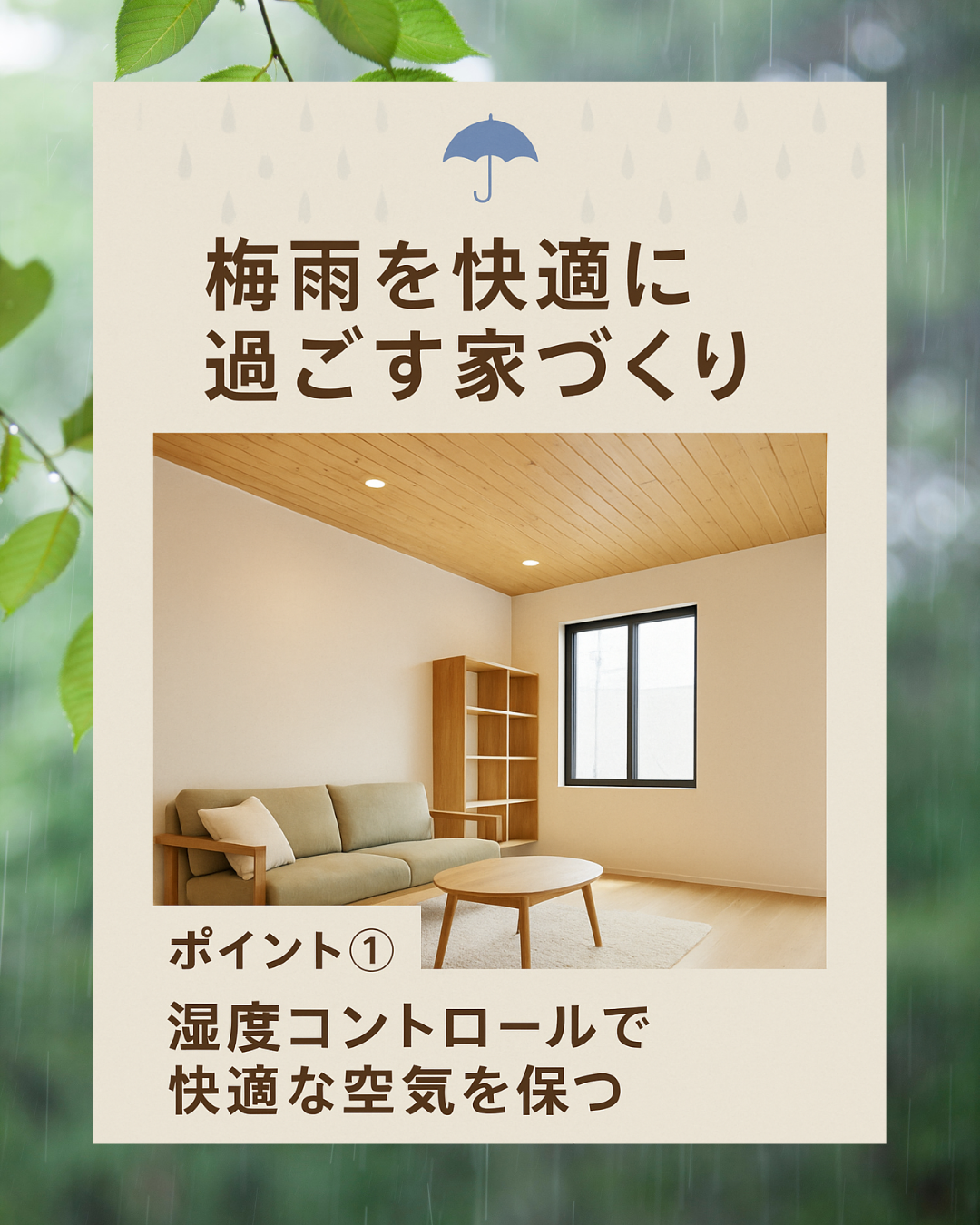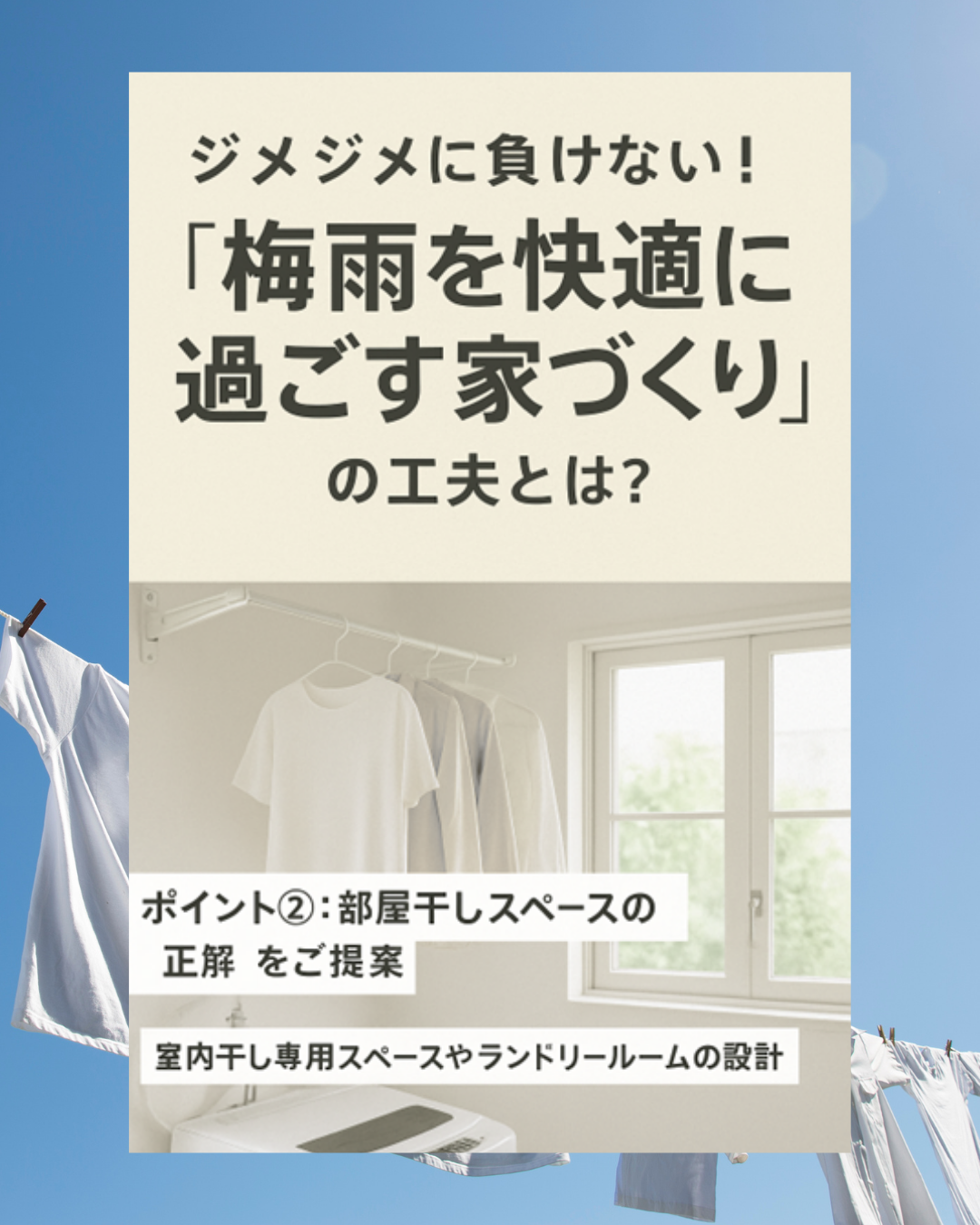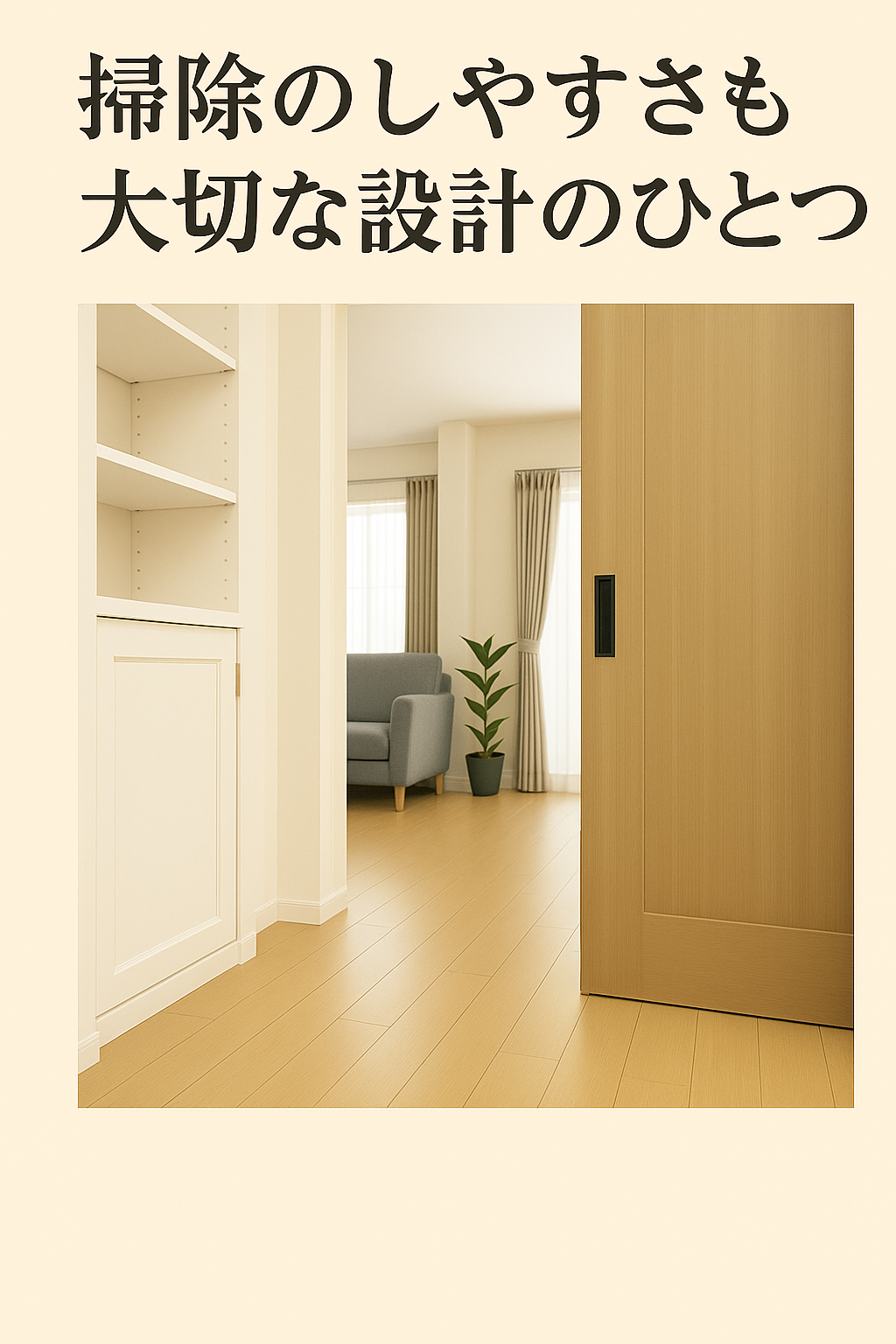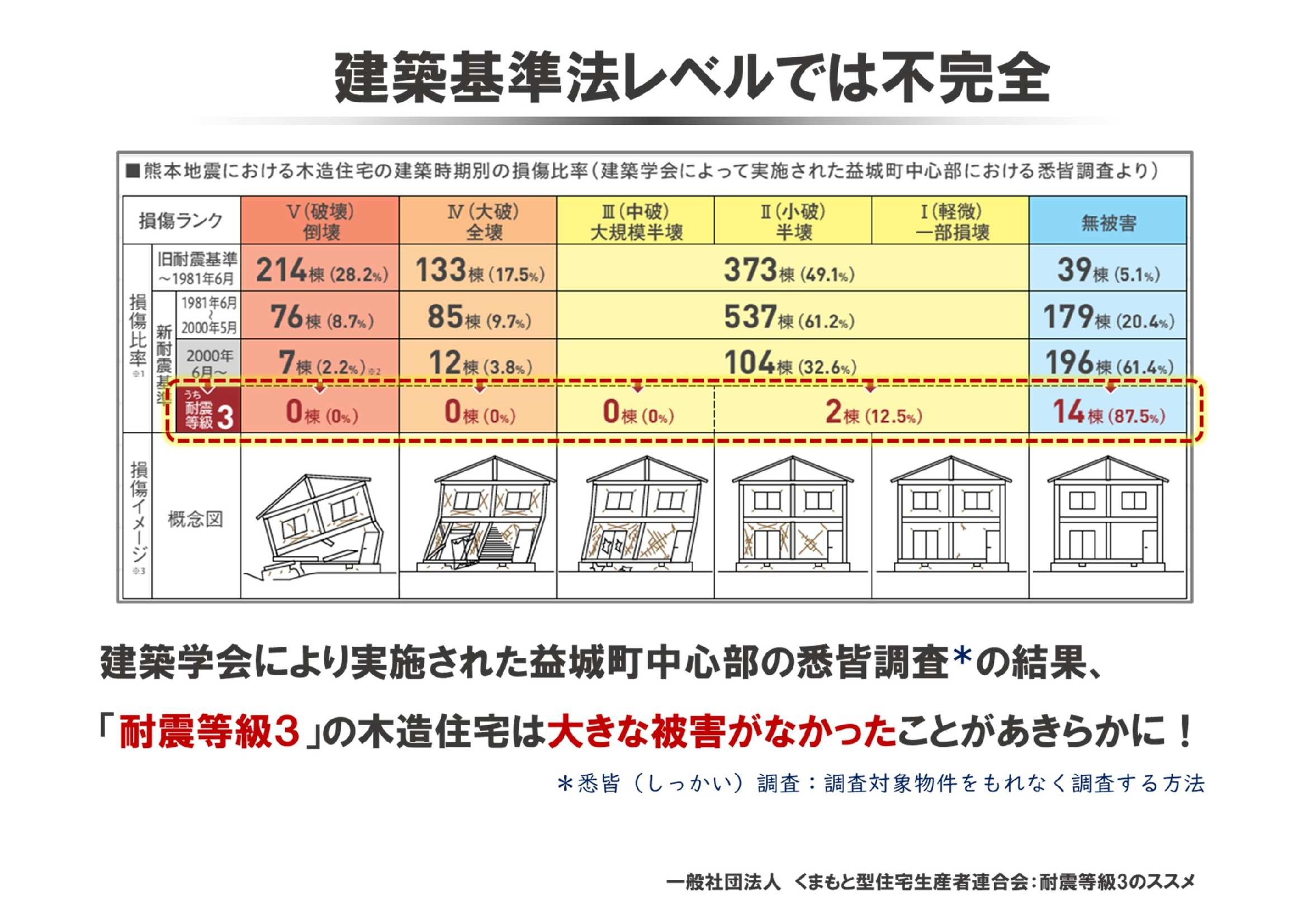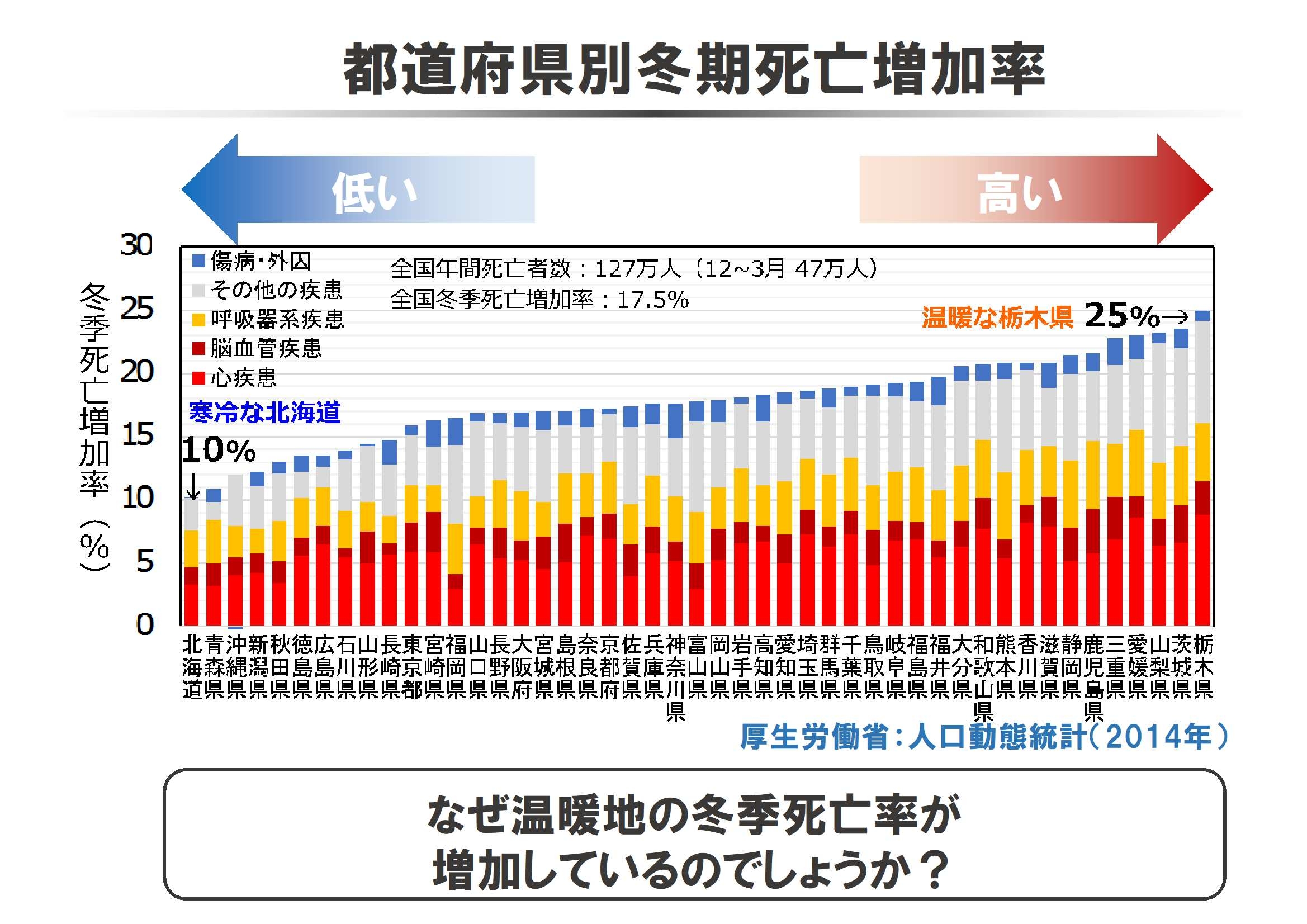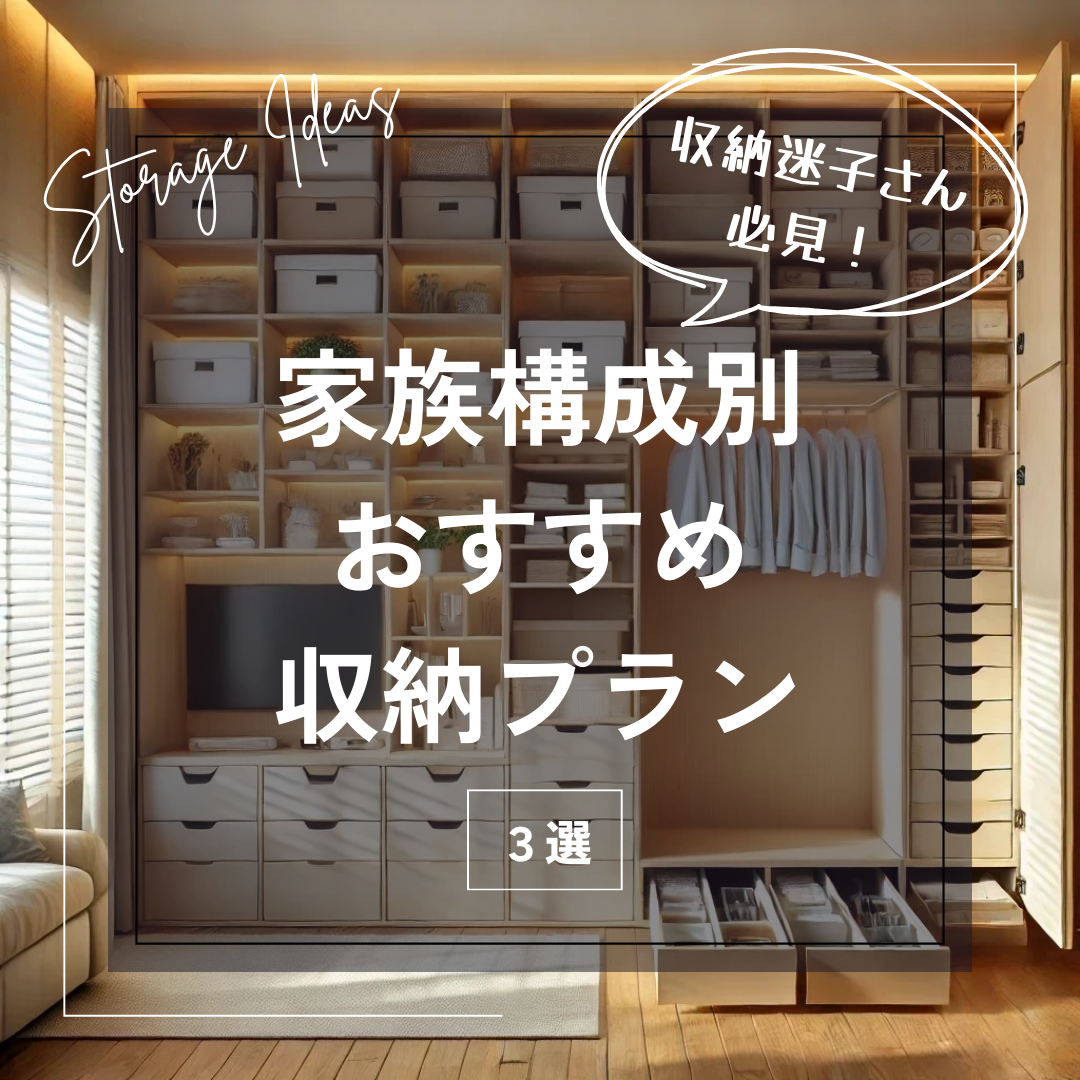♦家づくりの考え方
仕事に家事に育児にと、
毎日があっという間に過ぎていく共働き世帯の皆さま。
「もっと家事がラクになったら...」
「家の中の移動がスムーズなら...」
そんな風に感じたことはありませんか?
今回は、日々忙しく過ごすご家庭のために、
【暮らしを助けてくれる間取りアイデア】をご紹介します!
―――
物価上昇やエネルギー価格の高騰、そして相次ぐ災害のニュース。
子育て・老後・二世帯...将来のライフスタイルの変化。
――いま私たちは、「暮らしそのものを見直す転換期」に立たされています。
そんな中で注目されているのが、
【これからの暮らしにしなやかに対応できる、強くてやさしい家】です。
今回は、電気代や災害対策、そして将来設計まで考えた「これからの家づくり」についてお話しします。
#物価上昇 #エネルギー価格の高騰 #転換期 #災害対策 #将来設計
1|エネルギー価格が上がる今、「光熱費を自分でコントロールする家」へ
「電気代が前年比で1.5倍以上になった」
「節電しても請求額が下がらない」
こうした声は、決して他人事ではありません。
特に冬や夏のピーク時のエネルギー負担は、
今後さらに上がると予測されています。
そこで注目されているのが、
太陽光発電+蓄電池を備えた"自給自足型の住まい"。
晴れた日に自宅で発電し、余った電力は蓄電池に貯めて夜に活用。
電気の買取り価格は下がり電気料金が値上がりするいま、
作って使う時代、自家消費が注目されています。
また、停電時も冷蔵庫やスマホ充電、照明などの
"暮らしの基盤"を守ることができます。
もちろん、毎月の光熱費の削減にもつながります。
▶年間で10万円以上の節約になったというご家庭も!
「住むだけで家計がラクになる」
そんな家づくり、今や当たり前になりつつあるんです。
#太陽光発電 #蓄電池 #自家消費 #光熱費削減
2|災害リスクの時代に、「家が家族を守る」ための備えを
近年の大きな地震や台風、集中豪雨。
どこに住んでいても、"もしも"のリスクは常に隣り合わせです。
実は今、家づくりの価値観も変わってきています。
「デザイン重視」から、「安心・安全も兼ね備えた家」へ。
たとえば...
・地震への備え:耐震等級3の家で命を守る
・水害対策:浸水しづらい立地のご提案や、基礎高の設計
・断熱性:災害時の停電でも、室温を保ちやすい高断熱住宅
「家そのものが"家族の避難所"になる」ことが、
これからの家づくりに欠かせない視点になっています。
#地震対策 #耐震等級3 #水害対策 #断熱性 #高断熱住宅 #家族の避難所
3|ライフスタイルの変化にも対応。「長く愛せる、柔軟な住まい」
お子さまが成長して独立したあと。
親との同居が必要になったとき。
あるいは、夫婦ふたりになって身軽に暮らしたいと感じる頃――
"家は一度建てたら終わり"ではありません。
将来の変化に備えて、間取りを変更しやすい構造や、
家の一部を貸したり売却したりといった
選択肢を広げる設計が注目されています。
長期優良住宅や認定低炭素住宅など、
"資産価値が落ちにくく、長持ちする家"は、将来の備えとしても安心です。
#ライフスタイル変化 #柔軟な住まい #長期優良住宅 #認定低炭素住宅 #資産価値 #長持ちする家
(^^♪未来にやさしく、家族にやさしく。そんな家を一緒に考えませんか?
「今はまだ検討段階だけど...」
「資金面や時期が心配で、一歩踏み出せない」
そんなご相談も、白川建築では大歓迎です。
一人ひとりの暮らし方に合わせて、
無理のない予算で、"今"も"将来"も満たせる家づくりをご提案しています。
資料請求・個別相談・見学予約も、すべて無料でご案内しています。
お気軽にご相談ください(^^♪